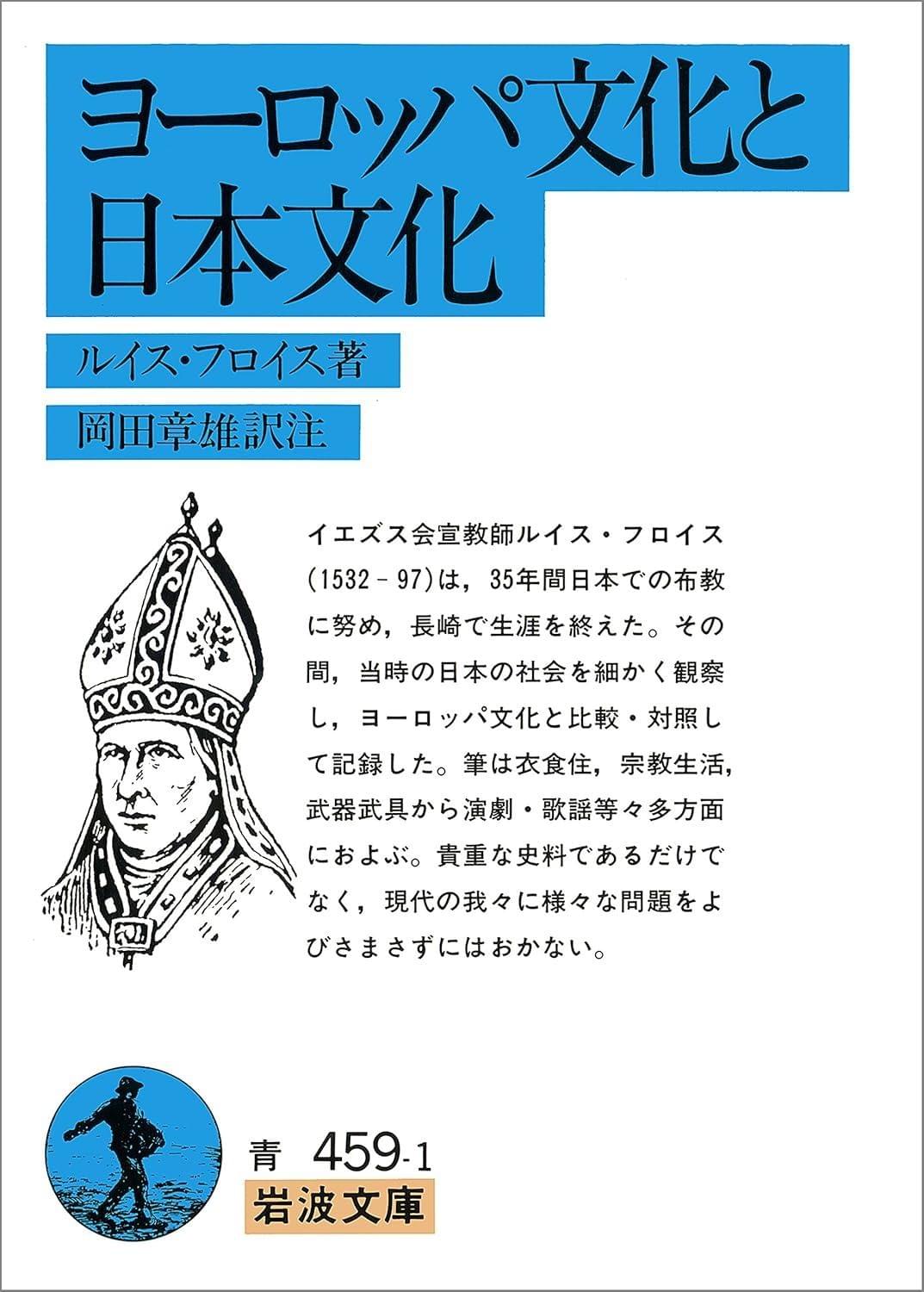皆さんは「ルイス・フロイス」という人物をご存じでしょうか。
日本史の時間に習ったような……という人が多いと(いいなと)思います。ざっくり言うと『戦国時代の日本にやってきたポルトガルの宣教師』です。あの織田信長や豊臣秀吉などといった当時の有名人にも会って、色んな記録を残しています。
この時代を扱った小説やゲームやドラマには、脇役や端役としてちらっと登場することも割と多いようです(大河ドラマでは4作に出ていますし、2026年に予定されている大河ドラマ『豊臣兄弟!』にも、もしかしたらちらりと出てくるかもしれませんね)
そんな在日歴が長く、日本の事情や風俗の隅々に通じたフロイスが書き残した(本国でも大変筆まめな性分だったとして知られているそうです)中に、
“Tratado em que se contem muito susintae abreviadamente algumas contradições e diferenças de custumes antre a gente de Europa e esta provincial de Japão”
というとても長いタイトルの小冊子があり、これが『ヨーロッパ文化と日本文化』というタイトルの大変わかりやすい文庫本になって、岩波文庫から出ているのです。
日本とヨーロッパを比較した本の中では最古の部類にあたるこの一冊を、今回は紹介していこうと思います。
まずは章立てから。おおよそですが男性、女性、児童、坊主(仏教の)、寺院など、食事や飲酒、武器、馬、病気や医者や薬、日本語(書物や紙やインク、手紙について)、家屋や庭園および果実、船に関すること、劇や歌や楽器、その他特殊なこと、と全十四章に分けられています。
その項目数はなんと約600!
馬や武器や船、日本語などに章を割いているところをみると、宣教師というよりは『外交官』のようなまなざしも見てとれます。
そのうち、仏教をけちょんけちょんに言っているのは、さすがカトリック宣教師だな、と思いますが、その他の条項では特に『ここが変だよ日本人!』みたいなことを言ってくることもなく、淡々と日欧の文化や慣習を比較する、ちょっとした事典のような1冊でもあります。
例を挙げると
「ヨーロッパでは女性は立ち上がって客人を迎える。日本では坐ったままで迎える」
(p59)
「われわれはすべてのものを手を使って食べる。日本人は女も男も、子供の時から二本の棒を用いて食べる」
(p92)※ヨーロッパでフォークを使うのは17世紀になってから
このように「ヨーロッパでは〜。日本では〜。」「われわれは〜。日本人は〜。」と比較する短い文章をたっぷり詰め込んだ、そしてその後ろに解説などもついた、比較的読みやすいものになっているのです。
神学校における、新任の宣教師が読む日本文化の副読本的な扱いだった、という説もあるようです。
そして、私達日本人が意外と知らない戦国時代の文化や習俗なども、事細かに、そしてわかりやすく伝えてくれる1冊になっているのです。
そのうちのひとつに、
「ヨーロッパでは娘や処女を閉じ込めておくことはきわめて大事なことで、厳格に行われる。日本では娘たちは両親にことわりもしないで一日でも幾日でも、ひとりで好きな所へ出かける」
(p50)
など、時折、何だか少し意外な(?)当時の日本の様子も(今の西洋で「娘を閉じ込めておくことは大事」だなんて言ったら大問題ですが)書かれています。
戦国時代の女子には、案外門限というものがなかったのかもしれませんね。
ただしこの後には割と悲惨な当時の妊娠・出産状況なども綴られていたりするので(びっくりするほどつぶさに観察されていたということですね)油断ならないわけですが……。
するすると読めてしまうので、色々と読み進めていくと、最後の『その他特殊なこと』の章にはなんと、
「我々は拇指(親指)または食指で鼻孔を綺麗にする。彼らは鼻孔が小さいために小指を用いておこなう」
(P191)
なんと、鼻をほじる指の違いまで観察するとは!(要するにこれは「日本人は鼻の穴が小さいので小指で鼻をほじっている」ということです。西洋人は、親指で鼻をほじるんですね……)
間違いなく、鼻をほじる指の違いを書き記すのは、宣教師のお仕事(布教活動以外にも色々な『外交的思惑』があったわけですがここでは省略します。気になる人は是非とも調べてみてくださいね!)ではないと思うのですが、たまにいますよね。こういう細かいところまで観察して上の方に律儀に報告してしまう人……。
そんなとても細かい(時々、『いやそれ何の役に立つんだろう…?』という)事柄も込みで、日本のあれこれを知るために書かれたこの小冊子、ポルトガルのキリシタン達が日本から撤退したりなどして忘れ去られていくのですが、マドリードの歴史アカデミーに『再発見』されて、今やこうして日本語でも読めるようになっています。
信長から秀吉の時代、激動の戦国時代の日本を、筆まめな外国人宣教師のまなざしでじっくりと細やかに観察した、来年の大河の予習にもぴったりなこの小さな1冊。
機会があったら是非とも、お手にとってみてください。
@akinona