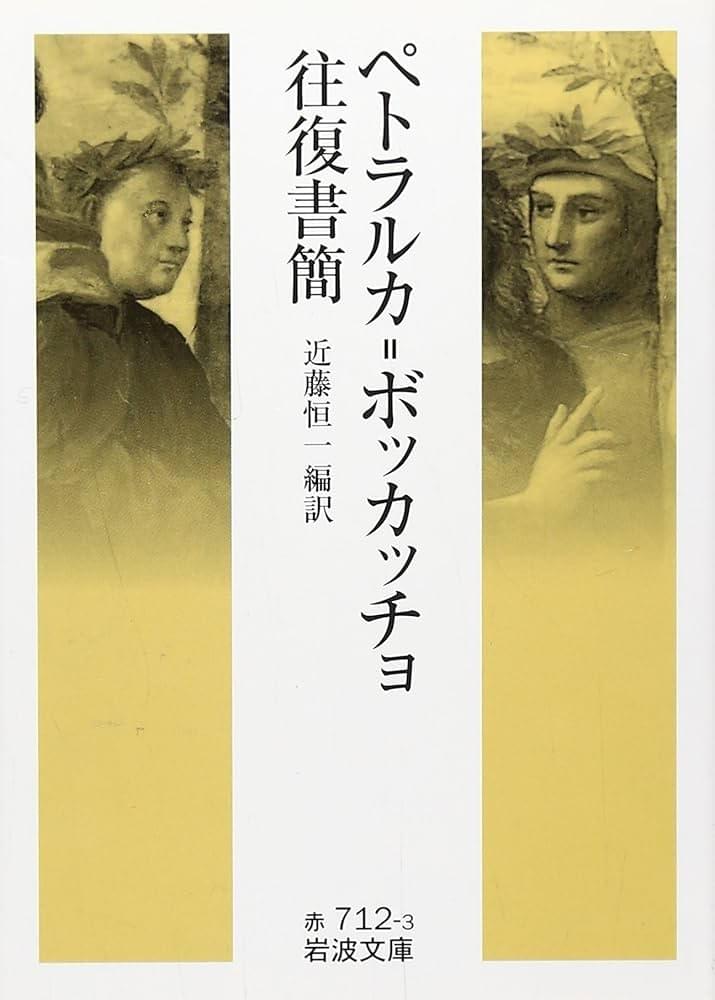ペトラルカ、と聞いても「世界史の時間にちらっと聞いたような……?」、そしてボッカッチョ(ボッカチオ、と表記されることも多いですね)ときいてもピンとこないけど「『デカメロン』の著者である」と聞けば「ああ、なんか聞いたような!」ってなる方は少なからずいるかと思います。
ルネサンスの二大文豪、といっても過言ではないこの二人が、実は生涯のペンパル(この言葉もすっかり死語になってしまいましたが、要するに『文通相手』ですね)だったことを知っている人は少ないでしょう。
「書簡はいつも、たのしい用事をもたらしてくれます。わたしが気晴らしを必要としているときは、とくにそうです」(p163)《ペトラルカからボッカッチョへ宛てた手紙の一文》
かたらルネサンス最高峰の詩人かつラテン語の大家であり(お堅いイメージがついて回ります)、かたやルネサンス屈指の大ヒット作品『デカメロン』(男と女のちょっとアダルティなお話も含まれます)の著者。
つまり、優しく頼れる先輩にして知的でクールな(ある意味このペトラルカこそがルネサンス最強のクールな詩人ですしね!)お師匠さん格な立場のペトラルカ、そして彼を慕う愛すべき熱血漢な後輩詩人ボッカッチョのやり取りした書簡集が岩波文庫から出ているのです。
その名も『ペトラルカ=ボッカッチョ往復書簡』(近藤恒一 編著)
時代は14世紀。15世紀末から16世紀初頭のルネサンス運動(数々の文人、そして何と言ってもレオナルド・ダ・ヴィンチとミケランジェロが競い合っていたあの時期です)がはじまる、その基盤とも言える文芸的な交流の証とも言えるこの文通。
ダ・ヴィンチとミケランジェロが仲良しだった、という記録は残っていませんが(むしろライバル意識バチバチだった模様)、このペトラルカとボッカッチョは大変仲が良く(ペトラルカが9歳年上です)、書簡をやり取りしていた痕跡が残っているのです。
ペトラルカは書簡集をきちんと残していますが、ボッカッチョにはそれがないため、比率はペトラルカの方が多めです。
そして昔は手紙一通届けるのもものすごく大変だったことが随所に書かれていて、現代みたいにメールで瞬時に資料などを添付してササッとやりとりしたり出来なかったからこそ、一通一通にかける情熱もとても大きいものとなっています。
二人とも当代随一の(そしてどちらも時代に翻弄された)文筆家。文章はとても美しく、時には愛情に溢れたユーモアさえも込められているのです。
『貴君はひとつだけ、わたしに借りがあります。愛情です。いや、これさえも借りではありません。じつはとっくに、貴君は借りを完済ずみです。ただし、貴君はいつもわたしの愛を受け取るので、いつもわたしに借りがあるというなら別です。でも、貴君はいつもわたしに愛を返してくれるので、何の借りもありません』(p239)《ペトラルカからボッカッチョへ宛てた手紙の一文》
ペスト大流行や不当な財産没収で流浪の身になった先輩ペトラルカを後輩ボッカッチョが励ましたり、政治のゴタゴタに巻き込まれて失脚しどん底にいる後輩ボッカッチョに『一緒に住まないか』とまで言ってくれる先輩ペトラルカ。
当代最高のルネサンス詩人二人の暖かく、むしろ熱い友愛の、生涯続くやりとりには、敬意を表さずにはいられません。
この二人の更に先輩詩人にあたるダンテの『神曲』を褒めすぎたボッカッチョが、「でもペトラルカ先輩の作品が一番ですから!」みたいな手紙をわざわざ出してフォローしちゃったりする(残念ながらその手紙自体は残っておらず、ペトラルカの返信の手紙が残っているので判明するのですが)のをみると、なんだかちょっと可愛いなあ、とさえ思えてしまうのです。
そのボッカッチョが翻訳したラテン語の自作品の本を心待ちにしながら息を引き取ったペトラルカや、そのペトラルカの優しい心遣いに満ちた遺言で贈られてきた「研究や夜仕事」のための金貨で買われたであろう、暖かい冬用の衣服にくるまって息を引きとったのであろうボッカッチョの言葉通りの『終生の』友情。
高尚な文学を執筆した何かよく知らない人達、ではなく、もう少し等身大な『人間』と『人間』の心のやり取りが詰まっているのが、この一冊になります。
解説の書き方にも非常に愛がこもっていて、編集者がこの両者を本当に敬愛してやまないんだろうなあ、と実感することができます。わかりやすい自伝や年表も詰めこまれているので、(本編と併せ読みすることをオススメします)ペトラルカもボッカッチョもよく知らないし………という人でも安心して読むことが出来ます。
ルネサンスという時代の先陣を切って駆け抜けていったこの二人の文豪、クールな先輩ペトラルカと熱血漢な後輩ボッカッチョの友情に満ちた書簡集、もしも気になる方がいたら、手に取ってゆっくりと読んでみてくださいね。
秋の夜長を彩る一冊にしてみてはいかがでしょうか。
@akinona