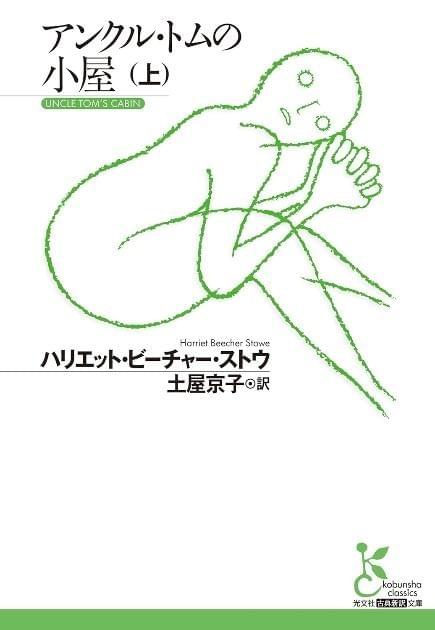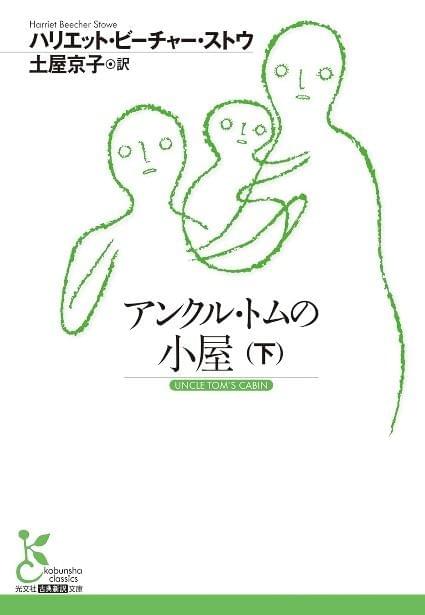タイトルだけは知っているのに読んだことないし、多分一生読まないんじゃな
いかな……という本、誰にでも1冊や2冊はあると思います。
その中でも特に多いのは「世界史や日本史の教科書に挙げられていた本」が
あると思います。なんかこう、小難しそうで、模範的で……と敬遠しがちなライ
ンナップになっている印象があります。(意外と面白いんですがね!)
今回紹介するのは、そんな本の代表格の一冊(な気がしている)、『アンクル・
トムの小屋』です。
著者は(私の世代では「ストウ夫人」と習いましたが今ではきちんとフルネー
ム表記されていて少し嬉しいですね)ハリエット・ビーチャー・ストウ。
奴隷制を文学の主題にしたアメリカで最初の小説であり、当時としては大変
先進的なベストセラー小説、ということですが、日本人の大半は、「で、どういう
物語?」となることでしょう。
「正直で有能、分別と信仰心を持つ奴隷頭のトムは、主人の借金返済の為に
奴隷商人に売却されることを受け入れる。一方、子供を売られることになった
女奴隷のイライザは自由の地であるカナダへの逃亡を図る」
あらすじから早速クライマックスですね。奴隷制のあったころのアメリカの奴
隷達にとって、逃げる先といえばまずカナダだった模様。
そもそもアメリカはキリスト教の国。奴隷制とは、はちゃめちゃに食い合わせ
が悪いのです。個人的にはその矛盾であり弱点であるところをがっつりと、これ
でもかというくらいに(そしてこの上なく『感情的に』)力いっぱい突いているのが
この物語の印象でもあります。
息子を連れて逃亡し、奴隷狩りに追われることになったイライザと息子のハリ
ー(小さくてもイケメンは高く売れるそうです。に、人間性とは……?)は、昨日
まで奴隷制度に賛成していて熱弁を振るっていた上院議員と、奴隷制に反対し
ている奥さんに助けられることになります(作中の名シーンのひとつと言われて
います)
そして機械の扱いが上手く農園で重宝されていたイライザの夫の混血奴隷の
ジョージ(見た目は白人に近い様です)も、別の極悪な主人の元で働かされる
羽目になって逃亡。途中で運良くイライザと合流し、ピストルでの大立ち回りな
ども経て、クエーカー教徒の助け等も得つつ、逃亡に成功するのです。
一方忠実なトムは妻クロウィや子供達と別れて売られていくのですが、あくま
でも善性の人なので決して文句は言いません。農場主の息子であるジョージ
坊ちゃん(イライザの夫のジョージとは別)は、自分を育ててくれたトムをいつか
買い戻すと約束するのです。
途中でエヴァンジェリンという小さな女の子を救ったことから、トムは彼女の家
に一旦は引き取られ、穏やかな暮らしを手に入れるのですが、エヴァンジェリン
とその父親が立て続けに死亡してしまい、奴隷へ対する愛情も理解もなかった
エヴァンジェリンの母親に、「財産整理」と称されて極悪非道な奴隷商人リグリ
ーに売り飛ばされてしまうのです。
それでも、あくまでも己の魂は神のものだと言い張る信心深いトムに、リグリ
ーとその手下達は殴る蹴るの暴行を加え、最初に暮らしていた穏やかな農場
の息子ジョージ坊ちゃんが助けに向かうも、間に合うことはなく天国へと旅立っ
ていきます。そしてジョージ坊ちゃんはトムを埋葬し、己の農場の奴隷達すべて
に自由を与えるのです。
もはや『黒いキリスト』とも言える非暴力と信仰の男トムには死による救済し
かなかったのだろうか、という疑問(私はキリスト教徒じゃないから、より、そう
感じるのかもしれません)、その傍らで、逃亡したことにより救われるジョージや
イライザは『決して肌が黒いわけではなく見目も良い』ことへの何かちょっとした
モヤモヤ感。
そして彼らが最終的に選んだのは「海外(アフリカのリベリア)への移住」。そ
れはある意味でアメリカによるアフリカへの(身勝手ともいえる)植民計画なの
です。つまり結局は共存できなかった、アメリカは彼らにとって自由の国でも祖
国でもなかった、せっかく国から自由を手に入れたというのに、最後の最後で
国の計画に加担してしまった、という結末で、本当によかったのか………など(
後日著者もまたこのエンディングに悩んだと言います)
更には、ここでは紹介しきれないほどに数多の個性的な女性達が登場する
家庭小説であり、いかなる時でも神を信じることを説く揺るぎないキリスト教文
学であり、奴隷制の弾劾をも兼ねた、『感情に訴えかける』1冊。新聞小説とし
て出されただけあって、複雑に入り組んでいるようで意外とヌルヌル読めてしま
います。この山あり谷ありの物語、出版して1年で30万部を超える大ベストセラ
ーになるのです。
そして本書の出版からちょうど10年後、南北戦争の最中にリンカーン大統領
は奴隷解放宣言を行います。著者のストウ夫人が
「では、この小さなご婦人が、この大戦争を引き起こした本を書いたのですね」
リンカーン大統領に招かれこう述べられた、という伝説まで生まれたといいま
す。
ちなみに、白人の元でせっせと正直に働いていたのに、売り払れた挙げ句最
後は虐待され死へと至る『アンクル・トム』は、『白人に迎合する黒人の象徴』と
して、現在では差別語として使われてしまっていることが多いようです。よく知ら
れる『ニガー(nigger)』よりも悪い意味です。
連載・発売当時のアメリカでもこの本を店に置いた本屋が町から追い出され
たり、大学で本が焼かれたりと、相当な物議を醸していたようです。
問題点も多い本作ですが、それは誰にとっても本意ではなさそうで、少し切な
いとさえ感じてしまいます。
最後に、作中の一文をご紹介します。
「当節、人道主義はいろいろと妙な形をとって現れることが多い。人道主義を謳
う人たちの言動にも、怪しげなものが後を絶たない」(上巻p26)
今も昔も変わらないものが、確かにそこかしこに散りばめられた名作。普通に
暮らしていても差別や排外主義が油断すると忍び寄ってくる今、この波瀾万丈
な『原点』を読んでみるのはいかがでしょうか。そして、
「この強大な時代の波、世界じゅうのあらゆる国において、またあらゆる言語に
おいて、人間の自由と平等を求める言葉にならぬ怨嗟の声をかきたてているこ
の強大な時代の波は、いったい何をもたらすのだろう?」(下巻p546)
今の時代にこの本を読むことが、一体読者である私たちに何をもたらすのか
をゆっくりと考えてみるのも良いと思います。
ライター:@akinona